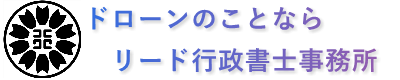「返済プロラタ」返済額を上手にコントロール
中小企業の経営者の皆様、日々の業務お疲れ様です。
事業を継続していく中で、複数の金融機関から借入れをされている方は多いのではないでしょうか
返済期日が近づくたびに、どの借入金から返済すれば良いのか、毎月の返済額はいくらになるのか、頭を悩ませているかもしれません。
そんな時に知っておくと役立つのが、今回のコラムでご紹介する「返済プロラタ」という考え方です。
「プロラタ」という言葉は、普段あまり聞きなれないかもしれません。
「プロラタ」はとてもシンプルで、あなたの事業をサポートしてくれるものです。
今回のコラムでは、この「返済プロラタ」について、専門用語をできるだけ使わず解説していきます。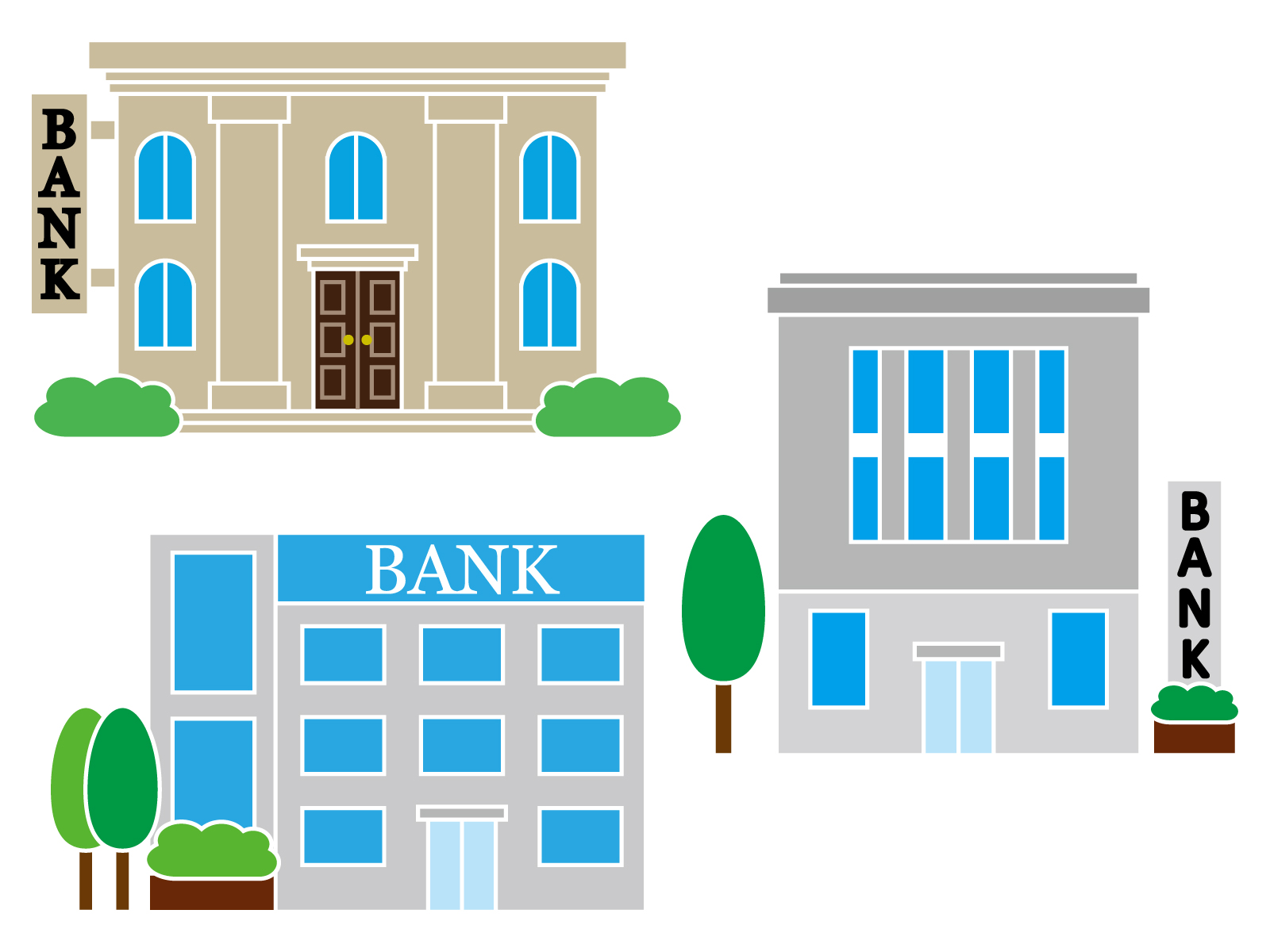
目次
1. 返済プロラタとは?
1-1. 返済プロラタの定義
1-2. 返済プロラタが活用される場面
2. なぜ返済プロラタが重要なのか?
2-1. 返済の公平性
2-2. 返済計画の立てやすさ
2-3. 金融機関との交渉を有利に進める
3. 返済プロラタの計算方法
3-1. 各借入金の残高を確認する
3-2. 各借入金の残高割合を計算する
3-3. 返済総額を各借入金の残高割合で分配する
4. 返済プロラタを活用する際の注意点
4-1. 借入条件の確認
4-2. 金融機関との合意
4-3. 専門家への相談
5. まとめ
1. 返済プロラタとは?
1-1. 返済プロラタの定義
「プロラタ」とは、簡単に言うと、「それぞれの割合に応じて分配する」 という意味です。
例えば、複数の借入金がある場合、それぞれの借入金の残高に応じて、公平に返済していくことを「返済プロラタ」といいます。
1-2. 返済プロラタが活用される場面
具体的には、以下のような場面で活用されます。
・複数の金融機関からの借入がある場合
複数の借入に対して、それぞれの借入残高の割合に応じて返済額を分配します。
・借入金の返済条件を変更する場合
金融機関と交渉し、返済条件を変更する際に、変更後の返済額をそれぞれの借入残高の割合に応じて分配します。
この方法を使うと、特定の借入金だけに返済が偏ることを防ぎ、公平かつ計画的に借入金を返済していくことができるようになります。
2. なぜ返済プロラタが重要なのか?
「返済プロラタ」は、借入金問題を抱える中小企業にとって、非常に重要な考え方です。その理由は主に以下の3つです。
2-1. 返済の公平性
複数の借入金がある場合、どこから返済すれば良いのか迷ってしまうことがあります。
また、急いで返済したい気持ちから、特定の借入金ばかりを優先して返済してしまうと、他の借入金の返済が滞ってしまうという悪循環に陥ってしまう可能性もあります。
「返済プロラタ」を用いることで、それぞれの借入金残高に応じて公平に返済額を分配するため、返済の偏りを防ぎ、計画的な返済が可能になります。
2-2. 返済計画の立てやすさ
「返済プロラタ」を使うと、毎月の返済総額を一定に保ちやすくなります。
そのため、返済計画を立てやすく、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
また、どの借入金に、いくら返済するのかが明確になるため、精神的な負担も軽減されます。
2-3. 金融機関との交渉を有利に進める
経営改善計画を立てる際には、金融機関との交渉が必要になることがあります。
「返済プロラタ」の考え方に基づいた返済計画を提示することで、金融機関に対して、公平で現実的な返済計画であることを理解してもらいやすくなります。
3. 返済プロラタの計算方法
「返済プロラタ」の計算は、以下の手順で行います。
とても簡単な計算なので、すぐに理解できるはずです。
3-1. 各借入金の残高を確認する
まず最初に、現在の借入金残高を確認します。
例えば、A銀行から300万円、B信用金庫から200万円の借入れがあるとします。
借入先と残高
A銀行 300万円
B信用金庫 200万円
合計 500万円
3-2. 各借入金の残高割合を計算する
次に、それぞれの借入金の残高が、借入金合計に占める割合を計算します。
A銀行の割合: 300万円 ÷ 500万円 = 0.6 (60%)
B信用金庫の割合: 200万円 ÷ 500万円 = 0.4 (40%)
3-3. 返済総額を各借入金の残高割合で分配する
毎月の返済総額が10万円の場合、それぞれの借入金への返済額は以下のようになります。
A銀行への返済額: 10万円 × 0.6 = 6万円
B信用金庫への返済額: 10万円 × 0.4 = 4万円
つまり、毎月10万円を返済する場合、A銀行に6万円、B信用金庫に4万円を返済することになります。
このように、それぞれの借入残高の割合に応じて返済額を分配するのが「返済プロラタ」です。
4. 返済プロラタを活用する際の注意点
「返済プロラタ」は、公平な返済計画を立てる上で非常に役立ちますが、いくつかの注意点もあります。
4-1. 借入条件の確認
借入金ごとに、返済期間や金利が異なる場合があります。
「返済プロラタ」は、あくまで返済額を分配する方法ですので、個々の借入条件を考慮した上で返済計画を立てることが大切です。
特に金融機関によって金利が大きく違う場合には、金利が高い借入金を優先して返済するなど、より有利な条件での返済を検討しましょう。
また、短期借入金と長期借入金では、返済計画の立て方も異なるため、それぞれの特性を考慮して、返済計画を立てるようにしましょう。
4-2. 金融機関との合意
返済計画を変更する際には、必ず金融機関と合意する必要があります。
「返済プロラタ」に基づいて返済計画を作成したとしても、金融機関が同意してくれなければ、その計画は実現できません。
事前に金融機関と十分な話し合いを行い、合意を得ることが重要です。
4-3. 専門家への相談
「返済プロラタ」を活用した返済計画は、専門的な知識が必要になる場合があります。
必要に応じて、当事業所などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
5. まとめ
今回のコラムでは、借入金返済の考え方である「返済プロラタ」について解説しました。
「返済プロラタ」は、難しい言葉のように聞こえるかもしれませんが、実はとてもシンプルで、公平かつ計画的な返済計画を立てるために有効な手段です。
借入金の返済計画で悩んでいる方は、ぜひこの「返済プロラタ」の考え方を参考に、ご自身の会社の経営改善に役立てていただければ幸いです。
当事務所では、中小企業の皆様の経営改善計画策定をサポートしております。
「返済プロラタ」についてのご相談はもちろん、その他にも様々な経営課題について、専門家として最適な解決策をご提案させていただきます。
お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。